| 危険物取扱者 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
例題集 NO10 解答・解説 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 例題は法令15問、物理化学10問、性質10問が1パターンになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【危険物に関する法令】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 問題1 | 次の文の( )内のA及びBに当てはまる語句の組合せとして、次のうち正しいのものはど れか。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 「アルコール類とは、1分子を構成する炭素の原子の数が( A )までの飽和1価アル コール(変形アルコールを含む。)をいい、その含有量が( B )未満の水溶液を除く。」 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | |||||||||||||||||||||||||||
|
(1) |
1〜3個 | 60% | ||||||||||||||||||||||||||
|
(2) |
2〜4個 | 60% | ||||||||||||||||||||||||||
|
(3) |
3〜6個 | 50% | ||||||||||||||||||||||||||
|
(4) |
2〜4個 | 50% | ||||||||||||||||||||||||||
|
(5) |
1〜3個 | 50% | ||||||||||||||||||||||||||
|
解説 |
(1)が正しい | |||||||||||||||||||||||||||
| 「アルコール類とは、1分子を構成する炭素の原子の数が( 1〜3個 )までの飽和1価アル コール(変形アルコールを含む。)をいい、その含有量が( 60% )未満の水溶液を除く。」 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 問題2 | 法令上、ある製造所において、第四類第二石油類を2,000L製造した場合、指定数量の倍 数の合計として次のうち正しいのはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(1) |
その危険物が非水溶性であれば10倍である。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(2) |
その危険物が水溶性であれば5倍である。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(3) |
その危険物が非水溶性であれば2倍である。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(4) |
その危険物が水溶性であれば2倍である。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(5) |
その危険物が非水溶性であれば1倍である。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
解説 |
(3)が正しい | |||||||||||||||||||||||||||
| 第四類第二石油類の指定数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非水溶性・・・1000L | ||||||||||||||||||||||||||||
| 水溶性・・・2000L | ||||||||||||||||||||||||||||
| その危険物が非水溶性であれば2倍である。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 問題3 | 製造所等を変更する場合、工事を着工できる時期として、次のうち正しいものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(1) |
仮使用の承認を受ければ、いつでも着工できる。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(2) |
変更許可申請後、10日経過すればいつでも着工できる。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(3) |
変更許可を申請すれば、いつでも着工できる。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(4) |
許可を受けるまで、着工できない。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(5) |
変更工事が位置、構造及び設備の基準に適合していればいつでも着工できる。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
解説 |
(4)が正しい | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造所等の設置及び変更は許可を申請をし、許可(許可書の交付)がおりて始めて工事が着工できる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
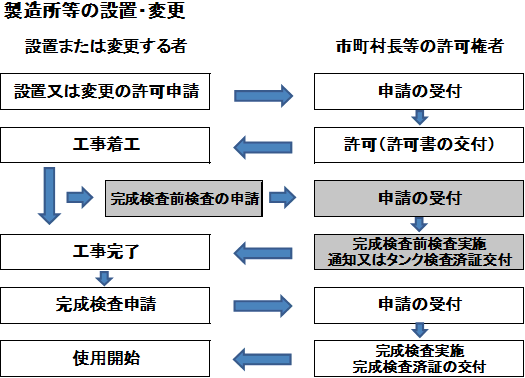
|
||||||||||||||||||||||||||||
| <完成検査前検査 > | ||||||||||||||||||||||||||||
| 製造所等で、液体の危険物を貯 蔵、取扱うタンクがある場合、全 体の完成検査を受ける前に市町 村長等に完成検査前検査申請を 行い、検査を受けなければならな い。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 法令上、製造所等に関して、市町村長等の認可を受けなければならない場合は、次のうち どれか。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
(1) |
危険物保安監督者を定めたとき。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(2) |
予防規定を定めたとき。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(3) |
危険物施設保安員を定めたとき。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(4) |
危険物保安統括管理者を定めたとき。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(5) |
定期点検の実施者を定めたとき。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
解説 |
(2)が正しい | |||||||||||||||||||||||||||
| 予防規定を定めたときは、市町村長等の認可を受けなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 問題5 | 法令上、製造所等における危険物の取扱いについて、次のうち正しいものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(1) |
製造所等の所有者が指示した場合、危険物取扱者以外の者でも、指定数量未満であれ ば、危険物を取り扱う事ができる。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(2) |
危険物取扱者以外の者が危険物を取り扱う場合には、指定数量未満であっても、甲種危険 物取扱者又は当該危険物を取り扱う事ができる乙種危険物取扱者の立会いが必要であ る。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(3) |
危険物取扱者以外の者が危険物を取り扱う場合、丙種危険物取扱者が立会うことができる のは、自ら取り扱える危険物に限られる。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(4) |
全ての乙種危険物取扱者は、丙種危険物取扱者が取り扱うことができる危険物を、自ら取り 扱う事ができる。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(5) |
危険物取扱者でなくても、指定数量未満であれば、すべての危険物を取り扱うことができる。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
解説 |
(2)が正しい | |||||||||||||||||||||||||||
| 危険物取扱者以外の者が危険物を取り扱う場合には、指定数量未満であっても、甲種危険 物取扱者又は当該危険物を取り扱う事ができる乙種危険物取扱者の立会いが必要である。1Lのガソリンを取扱うときも!! | ||||||||||||||||||||||||||||
|
(1) |
製造所等の場合、危険物取扱者以外の者は、指定数量未満であっても、危険物を取り扱う事ができない。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(3) |
丙種危険物取扱者は立会うことができない。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(4) |
丙種危険物取扱者が取り扱うことができる危険物を、自ら取り 扱う事ができるのは甲種及び、乙種4類の危険物取扱者である。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(5) |
指定数量未満であっても、甲種危険 物取扱者又は当該危険物を取り扱う事ができる乙種危険物取扱者の立会いが必要である。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 問題6 | 法令上、危険物保安監督者の業務について、次のうち誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(1) |
危険物施設保安員を置く製造所等にあっては、危険物施設保安員に必要な指示を行うこと。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(2) |
火災等の災害が発生した場合は、作業者を指揮して応急の措置を講ずるとともに、直ちに 消防機関等へ連絡すること。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(3) |
危険物の取扱作業の実施に際し、危険物の貯蔵又は取扱いに関する技術上の基準に適 合するように必要な指示を与えること。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(4) |
火災等の災害の防止に関し、当該製造所等に隣接する製造所等その他関連する施設の 関係者との間に連絡を保つこと。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(5) |
製造所等の位置、構造又は設備を変更する場合、これらに関する法令上の手続きをとること。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
解説 |
(5)が誤り | |||||||||||||||||||||||||||
| 法令上の手続きをとるのは、所有者等である。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 問題7 | 法令上、製造所等の定期点検に関する記述について、次のうち誤っているのはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(1) |
定期点検は、法第10条第4項に定める、危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に適合 しているかどうかについて実施する。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(2) |
地下タンクを有する一般取扱所は、定期点検を実施しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(3) |
地下タンクを有する給油取扱所は、定期点検を実施しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(4) |
免状の交付を受けていない者は、丙種危険物取扱者の立会いがあれば、定期点検(規則 で定める漏れの点検及び固定式の泡消火設備に関する点検を除く。)を行うことができる。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(5) |
点検記録の保存期間は、移動タンクの漏れの点検及び屋外貯蔵タンクの内部点検に係る 点検記録を除いて、3年間である。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
解説 |
(1)が誤り | |||||||||||||||||||||||||||
| 定期点検は、法第10条第4項に定める、製造所等の位置、構造及び設備が技術上の基準に適合 しているかどうかについて実施する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 貯蔵及び取扱いでなく、位置、構造及び設備の技術上の基準である。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 問題8 | 法令上、製造所等から一定の距離(保安距離)を保たなければならない旨の規定が設けら れている建築物等とその距離の組合せとして、正しいものは次のうちどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(1) |
病院 | ・・・・・ | 50m以上 | |||||||||||||||||||||||||
|
(2) |
高等学校 | ・・・・・ | 30m以上 | |||||||||||||||||||||||||
|
(3) |
小学校 | ・・・・・ | 20m以上 | |||||||||||||||||||||||||
|
(4) |
劇場 | ・・・・・ | 15m以上 | |||||||||||||||||||||||||
|
(5) |
使用電圧が7,000Vを超え、35,000V 以下の特別高圧架空電線 | ・・・・・ | 水平距離10m以上 | |||||||||||||||||||||||||
|
解説 |
(2)が正しい | |||||||||||||||||||||||||||
| 学校(幼稚園〜高等学校)・・・30m以上 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 問題9 | 指定数量の倍数が50を超えるガソリンを貯蔵する屋内貯蔵所の位置、構造及び設備の技 術上の基準について、法令上、次のうち誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(1) |
地盤面から軒までの高さが10m未満の平屋建とし、床は地盤面より低くしなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(2) |
壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造らなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(3) |
架台を設ける場合には、不燃材料で造るとともに、堅固な基礎に固定しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(4) |
床は、危険物が浸透しない構造とし、適当な傾斜をつけ、かつ、貯留設備を設けなければ ならない。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(5) |
屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ、天井を設 けてはならない。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
解説 |
(1)が誤り | |||||||||||||||||||||||||||
| 地盤面から軒までの高さが6m未満の平屋建とし、床は地盤面より高くしなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 問題10 | 法令上、移動タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準として、次のうち誤って いるものはどれか。 ただし、特例基準が適用されるものを除く。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(1) |
移動タンク貯蔵所は、屋外の防火上安全な場所又は難燃材料で造った建築物の地階に常 置しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(2) |
移動貯蔵タンクは、容量を30,000L以下とし、かつ、その内部に4,000L以下ごとに完全 な間仕切を厚さ3.2mm以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で設 けなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(3) |
移動貯蔵タンクのマンホール及び注入口のふたは、厚さ3.2mm以上の鋼板又は同等以 上の機械的性質を有する材料で造らなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(4) |
移動貯蔵タンクの外面には、さび止めのための塗装をしなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(5) |
静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険の移動貯蔵タンクには、接地導線を 設けなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
解説 |
(1)が誤り | |||||||||||||||||||||||||||
| 移動タンク貯蔵所は、屋外の防火上安全な場所又は壁、床、はり及び屋根を耐火構造とし、若しくは不燃材料で造つ た建築物の一階に常置すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 問題11 | 製造所等における標識、掲示板についての説明で、次のうち誤っているのはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(1) |
地色が赤の掲示板は、「火気厳禁」又は「火気注意」を示している。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(2) |
地色が青の掲示板は、「禁水」を示している。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(3) |
指定数量以上の危険物を運搬する場合には、車両の前後の見やすい箇所に0.3m平方 の黒地に黄色の反射塗料等で「危」と表示をしなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(4) |
「禁水」と表示されている貯蔵所は、アルカリ金属の過酸化物又は禁水性物品を貯蔵してい るものである。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(5) |
「火気厳禁」の掲示板が掲げられている貯蔵所は、第三類又は第四類の危険物のみを貯蔵 しているものである。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
解説 |
(5)が誤り | |||||||||||||||||||||||||||
| 「火気厳禁」の掲示板が掲げられている貯蔵所は、第四類又は第五類の危険物のみを貯蔵 しているものである。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 問題12 | 法令上、製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いのすべてに共通する技術上の基準に ついて、次のうち正しいものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(1) |
危険物のくずやかす等は、一日一回以上危険物の性質に応じて安全な場所で廃棄その他 適当な処置をしなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(2) |
危険物が残存し、又は残存するおそれがある設備、機械器具、容器を修理する場合は、換 気をしながら行わなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(3) |
危険物を保護液中に保存する場合は、危険物の確認のため、その一部を保護液中から露 出させなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(4) |
貯留設備又は油分離装置にたまった危険物は、十分希釈して濃度を下げてから下水等に 排出しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(5) |
製造所等においては、一切の火気を使用してはならない。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
解説 |
(1)が正しい | |||||||||||||||||||||||||||
| 危険物のくずやかす等は、一日一回以上危険物の性質に応じて安全な場所で廃棄その他 適当な処置をしなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
(2) |
危険物が残存し、又は残存するおそれがある設備、機械器具、容器を修理する場合は、安全な場所において、危険物を完全に除去した後に行うこと。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(3) |
危険物を保護液中に保存する場合は、危険物が保護液から露出しないようにすること。 | |||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 貯留設備又は油分離装置にたまつた危険物は、あふれないように随時くみ上げること。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(5) |
製造所等では、みだりに火気を使用しないこと。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 問題13 | 法令上、顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準について、次のうち 誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(1) |
顧客用固定給油設備を使用して、顧客に自ら自動車等に給油させることができる。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(2) |
顧客用固定給油設備を使用して、顧客に自らガソリンを運搬容器に詰め替えさせることができる。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(3) |
顧客用固定給油設備を使用して、顧客に自ら移動貯蔵タンクに軽油を注入させることはで きない。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(4) |
顧客用固定給油設備以外の固定給油設備を使用して、顧客に自ら自動車等に給油させる ことはできない。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(5) |
制御卓にて、顧客自らによる給油作業を監視し、及び制御し、並びに顧客に対して必要な 指示を行わなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
解説 |
(2)が誤り | |||||||||||||||||||||||||||
| 顧客用固定給油設備を使用して、顧客に自らガソリンを運搬容器に詰め替えさせることができない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| <顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準> | ||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客に自ら自動車若しくは原動機付自転車に給油させ、又は灯油若しくは軽油を 容器に詰め替えさせることのできる給油取扱所とする。よってガソリンを運搬容器に詰め替えさせることができない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 問題14 | 法令上、製造所等の法令違反とそれに対して市町村長等から命ぜられる命令の組合せと して誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(1) |
定期点検の未実施 | ・・・・・ | 製造所等の使用停止命令 | |||||||||||||||||||||||||
|
(2) |
亡失した免状の再交付申請未実施 | ・・・・・ | 免状返納命令 | |||||||||||||||||||||||||
|
(3) |
製造所等の位置、構造及び設備が技術上の 基準に違反しているとき | ・・・・・ | 危険物施設の基準適合命令 | |||||||||||||||||||||||||
|
(4) |
危険物に係る事故の発生に対し、応急措置を 講じていないとき | ・・・・・ | 危険物施設の応急措置命令 | |||||||||||||||||||||||||
|
(5) |
危険物の無許可貯蔵又は取扱い | ・・・・・ | 危険物の除去命令 | |||||||||||||||||||||||||
|
解説 |
(2)が誤り | |||||||||||||||||||||||||||
| 亡失した免状の再交付申請未実施について特に定めはない。資格を失うだけである。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 問題15 | 法令上、製造所等において、火災又は危険物の流出等の災害が発生した場合の応急の措 置等について、次のうち誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(1) |
所有者等は、火災が発生したときは、直ちに火災現場に対する給水のため、公共水道の開 閉弁を開けなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(2) |
所有者等は、危険物の流出その他の事故が発生したときは、直ちに、引き続く危険物の流 出の防止その他災害の発生の防止のための応急措置を講じなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(3) |
危険物保安監督者は火災等の災害が発生した場合は、作業者を指揮して応急の措置を講 じなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(4) |
所有者等は、危険物施設保安員に、火災が発生したときは、危険物保安監督者と協力し て、応急措置を講じなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(5) |
危険物の流出その他の事故を発見した者は、直ちに、その旨を消防署等に通報しなけれ ばならない。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
解説 |
(1)が誤り | |||||||||||||||||||||||||||
| 公共水道の開 閉弁を開けなければならない権限を持つのは消防長、消防署長である。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【基礎的な物理学及び基礎的な化学】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 問題16 | 沸点について、次のうち正しいものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(1) |
沸点は、外圧が高くなるほど低くなる。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(2) |
水に食塩を溶かした溶液の1気圧における沸点は、100℃より低い。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(3) |
沸点とは、液体の飽和蒸気圧と外圧とが等しくなったときの液温をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(4) |
可燃性液体の沸点はすべて100℃より低い。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(5) |
沸点が高い液体ほど蒸発しやすい。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
解説 |
(3)が正しい | |||||||||||||||||||||||||||
| 沸点とは、液体の飽和蒸気圧と外圧とが等しくなったときの液温をいう。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 問題17 | 熱容量について、次のうち正しいものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(1) |
物体の温度を1 K上げるのに必要な熱量である。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(2) |
容器の比熱のことである。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(3) |
物体に1 Jの熱を与えたときの温度上昇率のことである。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(4) |
物質1 kgの比熱のことである。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(5) |
比熱に密度を乗じたものである。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
解説 |
(1)が正しい | |||||||||||||||||||||||||||
| 物体の温度を1(K)上げるのに必要な熱量をその物体の熱容量(J/K)という。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (K)ケルビン | ||||||||||||||||||||||||||||
| 問題18 | 次の文の( )内のA、Bに当てはまる語句の組合せとして正しいものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 「物体は熱源との間にある流体が存在するときは、流体は一般に温度が高くなると比重が小 さくなるため上方に移動し、これにより熱が伝わる現象を熱の( A )という。しかし物体と 熱源との間に何もない真空の状態でも熱は伝わる。太陽により地上の物体が温められるの はこの例であり、この現象を熱の( B )という。」 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | |||||||||||||||||||||||||||
|
(1) |
対流 | 伝導 | ||||||||||||||||||||||||||
|
(2) |
伝導 | 放射 | ||||||||||||||||||||||||||
|
(3) |
伝導 | 対流 | ||||||||||||||||||||||||||
|
(4) |
対流 | 放射 | ||||||||||||||||||||||||||
|
(5) |
放射 | 伝導 | ||||||||||||||||||||||||||
|
解説 |
(4)が正しい | |||||||||||||||||||||||||||
| 「物体は熱源との間にある流体が存在するときは、流体は一般に温度が高くなると比重が小 さくなるため上方に移動し、これにより熱が伝わる現象を熱の( 対流 )という。しかし物体と 熱源との間に何もない真空の状態でも熱は伝わる。太陽により地上の物体が温められるの はこの例であり、この現象を熱の( 放射 )という。」 | ||||||||||||||||||||||||||||
| <伝導> | ||||||||||||||||||||||||||||
| 熱が物質中を伝わっていく現象を伝導といい、熱が伝導する度合いは物質によって異なり、伝導 の度合いを表す数値を熱伝導率という。熱伝導率は、固体が比較的大きく、次に液体、気体の順 で小さくなる。熱伝導率が大きいとは、その物質が熱を伝えやすいことを意味する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| <対流> | ||||||||||||||||||||||||||||
| 液体、気体などの温度差によって液体、気体が移動する現象を対流という。 液体や気体は加熱されると、その部分が膨張して密度が小さくなり上昇し、そのあと重い低温部 分が流れ込んでくる。お風呂でお湯を沸かすとき、火災現場で風が起こったりするのは対流効果 の例である。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| <放射> | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一般に、熱せられた物体が放射熱を出して他の物体に熱を与えること、直接触ってもいな いのに熱が伝わってくる熱の移動を放射(ふく射)という。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 問題19 | 静電気について、次の説明のうち誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(1) |
放電火花が可燃性物質の着火源になることはない。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(2) |
静電気の電荷間に働く力はクーロン力である。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(3) |
帯電した物体の電荷が移動しない場合の電気を静電気という。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(4) |
二つ以上の物体が摩擦、衝突、はく離等の接触分離をすることにより静電気が発生する。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(5) |
静電気の帯電防止策として、接地する方法がある。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
解説 |
(1)が誤り | |||||||||||||||||||||||||||
| 放電火花が可燃性物質の着火源になることはよくある。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 問題20 | 0.5mol/Lの硫酸水溶液200mlを、濃度98wt%の濃硫酸からつくろうとする場合、必要な 濃硫酸の量として次のうち正しいものはどれか。 ただし、H2SO4の分子量は98、濃硫酸の密度は2.0g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(1) |
1.0ml | |||||||||||||||||||||||||||
|
(2) |
2.0ml | |||||||||||||||||||||||||||
|
(3) |
3.0ml | |||||||||||||||||||||||||||
|
(4) |
4.0ml | |||||||||||||||||||||||||||
|
(5) |
5.0ml | |||||||||||||||||||||||||||
|
解説 |
(5)が正しい | |||||||||||||||||||||||||||
| molの定番の問題である。答えを覚える! | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5mol/Lを200ml(0.2L)作るということは、 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 硫酸H2SO4が0.2×0.5=0.1mol必要となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 分子量98なので、0.1mol、つまり9.8g必要ということになる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 濃度が98wt%の濃硫酸を使うということなので、 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (必要な濃硫酸g)×0.98=9.8になればよいので | ||||||||||||||||||||||||||||
| (必要な濃硫酸g)=10g 濃硫酸の密度が2.0g/cm3ならば、 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (必要な濃硫酸cm3)=10÷2.0=5.0cm3=5.0ml | ||||||||||||||||||||||||||||
| 問題21 | 次のうち、鉄よりもイオン化傾向が大きいものはいくつあるか。 | |||||||||||||||||||||||||||
| マグネシウム 銀 カリウム 白金 亜鉛 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
(1) |
1つ | |||||||||||||||||||||||||||
|
(2) |
2つ | |||||||||||||||||||||||||||
|
(3) |
3つ | |||||||||||||||||||||||||||
|
(4) |
4つ | |||||||||||||||||||||||||||
|
(5) |
5つ | |||||||||||||||||||||||||||
|
解説 |
(3)が正しい | |||||||||||||||||||||||||||
| マグネシウム 銀 カリウム 白金 亜鉛 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 金属の単体が、水または水溶液中で陽イオンとなる性質の強さを、その金属のイオン化傾向という、またイオン 化傾向の大きさの順に並べたものをイオン化列という。 | ||||||||||||||||||||||||||||
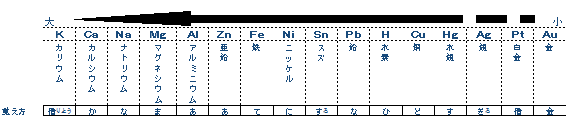
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 問題22 | 燃焼に関する一般的説明として、次のうち誤っているのものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(1) |
静電気が発生しやすい物質ほど、激しく燃焼する。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(2) |
高引火点の可燃性液体でも、綿糸に染み込ませると容易に着火する。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(3) |
分解又は蒸発により可燃性蒸気を発生しやすい物質は、着火しやすい。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(4) |
固体の可燃物に固体の酸化剤が混在すると、可燃物単独よりも激しく燃焼する。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(5) |
拡散燃焼では、酸素の供給が大きいほど激しく燃焼する。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
解説 |
(1)が誤り | |||||||||||||||||||||||||||
| 静電気が発生しやすい物質と燃焼の難易は関係ない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 問題23 | 引火、発火等について、次のうち誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(1) |
同一の可燃性物質においては、一般に発火点のほうが引火点よりも高い数値を示す。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(2) |
発火点とは、空気中で可燃物を加熱したとき、火源がなくても自ら発火する最低の温度をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(3) |
燃焼点とは、可燃性液体が継続して燃焼するのに必要な濃度の蒸気を発生する液温をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(4) |
引火点とは、可燃性液体が燃焼範囲の上限値の濃度の蒸気を発生する液温をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(5) |
同一の可燃性物質においては、一般に引火点よりも燃焼点のほうが高い数値を示す。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
解説 |
(4)が誤り | |||||||||||||||||||||||||||
| 引火点とは、可燃性液体が燃焼範囲の下限値の濃度の蒸気を発生する液温をいう。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 問題24 | 消火について、次のうち誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(1) |
燃焼の三要素のうち、1つの要素を取り除けば消火できる。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(2) |
窒息消火による消火とは、酸素の濃度を低下させ消火する方法である。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(3) |
水は比熱及び気化熱が大きいため、冷却効果が大きい。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(4) |
セルロイドのように分子中に酸素を含有している物質には、窒息消火は効果的である。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(5) |
二酸化炭素消火剤の主たる消火効果は、窒息である。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
解説 |
(4)が誤り | |||||||||||||||||||||||||||
| セルロイドのように分子中に酸素を含有している物質には、窒息消火は不適である。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 窒息消火は酸素を絶つということなので、酸素を含有している物質には有効でない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 問題25 | 触媒による化学反応の一般的説明として、次のうち正しい組み合わせはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||
| A 化学反応の平衡に影響を及ぼさない。 。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B 反応の活性化エネルギーを大きくする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C 反応速度を大きくする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D 反応熱は触媒によって小さくなる | ||||||||||||||||||||||||||||
|
(1) |
A B | |||||||||||||||||||||||||||
|
(2) |
A C | |||||||||||||||||||||||||||
|
(3) |
B C | |||||||||||||||||||||||||||
|
(4) |
B D | |||||||||||||||||||||||||||
|
(5) |
C D | |||||||||||||||||||||||||||
|
解説 |
(2)が正しい | |||||||||||||||||||||||||||
| A 化学反応の平衡に影響を及ぼさない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B 反応の活性化エネルギーを大きくする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C 反応速度を大きくする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D 反応熱は触媒によって小さくなる 。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| <触媒> | ||||||||||||||||||||||||||||
| 反応の前後でそれ自身は変化せず、反応速度を速める物質を触媒と呼び、反応の進行する方向(化学平衡)を変えることはない。触媒を用いると反応機構が変化し、活性化エネルギーより小さい経路で反応が進むため反応は速くなる。反応熱は反応物と生成物の生成エネルギーの差で決まるため、触媒を用いても反応熱の値は変化しない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ポイント |
マル覚え!! | |||||||||||||||||||||||||||
| 【危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 問題26 | 危険物の類ごとに共通する性状について、次のうち正しいものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(1) |
第一類の危険物は、強還元性の液体である。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(2) |
第二類の危険物は、燃えやすい固体である。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(3) |
第三類の危険物は、水と反応しない不燃性の液体である。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(4) |
第五類の危険物は、強酸化性の固体である。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(5) |
第六類の危険物は、可燃性の固体である。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
解説 |
(2)が正しい | |||||||||||||||||||||||||||
| 第二類の危険物は、燃えやすい固体である。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 問題27 | 第四類の危険物の性状として、次のうち誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(1) |
非水溶性のものは、流動、かくはんなどにより静電気が発生し、蓄積する。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(2) |
水溶性のものは、水で薄めると引火点が低くなる。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(3) |
常温(20℃)で、ほとんどのものは液状である。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(4) |
蒸気は低所に滞留しやすい。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(5) |
液体の比重は、1より小さいものが多い。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
解説 |
(2)が誤り | |||||||||||||||||||||||||||
| 水溶性のものは、水で薄めると引火点が高くなる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 問題28 | 第四類の危険物の貯蔵、取扱いの方法について、次のA〜Dのうち正しいもののみを掲げ ている組合せはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||
| A 引火点の低い物質を屋内で取扱う場合には、換気を十分にする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B 屋内の可燃性蒸気の滞留する恐れのある場所は、その蒸気を屋外の地表に近い部分に排出する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C 容器に収納する場合、容器に通気孔を設ける。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D 可燃性蒸気が滞留しやすい場所に設ける電気設備は、防爆構造とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
(1) |
A B | |||||||||||||||||||||||||||
|
(2) |
A C | |||||||||||||||||||||||||||
|
(3) |
A D | |||||||||||||||||||||||||||
|
(4) |
B C | |||||||||||||||||||||||||||
|
(5) |
C D | |||||||||||||||||||||||||||
|
解説 |
(3)が正しい | |||||||||||||||||||||||||||
| A 引火点の低い物質を屋内で取扱う場合には、換気を十分にする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B 屋内の可燃性蒸気の滞留する恐れのある場所は、その蒸気を屋外の高所に排出する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C 容器に収納する場合、容器を密栓する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D 可燃性蒸気が滞留しやすい場所に設ける電気設備は、防爆構造とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 問題29 | ジエチルエーテルの貯蔵又は取扱いに関する注意事項とその理由の組合せとして、次のう ち適切なものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 注意事項 | 理由 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(1) |
水中に保存する。 | 空気中で自然発火するから。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
(2) |
貯蔵する容器は金属製のものを使用しない。 | 金属と反応して、発火又は爆発する恐れがあるから。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
(3) |
容器への詰め替えは流速を速くし、短時間で行う。 | 流速を速くすれば静電気が発生しにくいから。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
(4) |
室内で取扱う場合は、特に高所の換気を十分行う。 | 発生する蒸気は空気よりも軽いので高所に滞留するから。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
(5) |
空気に触れないようにし、密閉容器で冷暗所に保存する。 | 過酸化物が生成し、爆発する恐れがあるから。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
解説 |
(5)が正しい | |||||||||||||||||||||||||||
| <ジエチルエーテル>特殊引火物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 無色の液体 特有の甘い刺激臭 蒸気には麻酔性がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 水にわずかに溶け、アルコールによく溶ける。揮発しやすく、刺激臭がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 引火の危険性が大きい、 日光にさらしたり空気と長く接触すると過酸化物を生じて、加熱、衝撃などにより爆発の危険性がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 問題30 | 自動車ガソリンの性状について、次のうち誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(1) |
燃焼範囲は、33〜44vol%である。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(2) |
流動、摩擦等により静電気が発生しやすい。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(3) |
引火点は、−40℃以下である。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(4) |
蒸気は空気より重い。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(5) |
水面に流れたものは広がりやすい。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
解説 |
(1)が誤り | |||||||||||||||||||||||||||
| 燃焼範囲は、1.4〜7.6vol%である | ||||||||||||||||||||||||||||
| <ガソリン>第一石油類 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 無色、 特臭のある液体 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 水に溶けず、ゴム、油脂などを溶かす。 炭素数4〜10の炭化水素の混合物。 自動車用(オレンジ)、工業用(無色)、航空機用(緑色)の3種類に分けられる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 極めて引火しやすい。 蒸気は空気より重いので低所に滞留しやすい。 電気の不良導体、流動により静電気を発生しやすい。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 比重 0.75、 蒸気比重 3〜4、 引火点 −40℃、 発火点 300℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ポイント |
ガソリンの数値は覚える!! | |||||||||||||||||||||||||||
| 問題31 | メタノールとエタノールの性状について、次のうち誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(1) |
メタノールは毒性をもつ。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(2) |
いずれも揮発性で無色の液体である。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(3) |
いずれも引火点は常温(20℃)以下である。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(4) |
いずれも水溶性で濃度が低いほど引火点が下がる。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(5) |
いずれも消火には、一般の泡消火剤は不適切である。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
解説 |
(4)が誤り | |||||||||||||||||||||||||||
| いずれも水溶性で濃度が低いほど引火点が上がる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 水で薄めれば引火点は上がるということである。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 問題32 | 軽油の性状について、次のうち誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(1) |
沸点は水よりも高い。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(2) |
水より軽い。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(3) |
蒸気は空気よりわずかに軽い。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(4) |
ディーゼル機関等で燃料として用いられる。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(5) |
引火点は45℃以上である。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
解説 |
(3)が誤り | |||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気は空気より重い。第4類の危険物の蒸気はすべて空気より重い! | ||||||||||||||||||||||||||||
| <軽油>第二石油類 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淡黄色、または淡褐色の液体 石油臭 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 炭化水素を主成分とした混合物。 水に溶けない。 水より軽い。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 加温などにより液温が引火点以上になると引火の危険性はガソリン同様。霧状になって浮遊するとき、布などに染みこんだときは空気との接触面積が多くなり、危険性が増大。 流動で静電気が発生。 ガソリンが混合されたものは引火しやすい。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気比重 4.5、 引火点 50〜70℃、 発火点 220℃、 燃焼範囲 1.2〜6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 問題33 | 次の文の下線部分A〜Eのうち、誤っている箇所はどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 「C重油は A 褐色又は暗褐色の液体で、 B 引火点は70℃以上と高く、 C 常温(20 ℃)で取扱えば引火の危険性は少ないが、いったん燃え始めると、 D 液温が高くなって いるので消火が困難になる場合がある。大量に燃えている火災の消火には、 E 棒状注水 が適している。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
(1) |
A | |||||||||||||||||||||||||||
|
(2) |
B | |||||||||||||||||||||||||||
|
(3) |
C | |||||||||||||||||||||||||||
|
(4) |
D | |||||||||||||||||||||||||||
|
(5) |
E | |||||||||||||||||||||||||||
|
解説 |
(5)が誤り | |||||||||||||||||||||||||||
| 水による消火は不適である。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 問題34 | 動植物油類の中には自然発火を起こすものがある。自然発火を起こしやすいものは、次の うちどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(1) |
容器に入った油を、長時間直射日光にさらしていたとき。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(2) |
油の入った容器を、ふたをせずに置いていたとき。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(3) |
容器に入った油を、湿気の多い場所で貯蔵したとき。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(4) |
容器からこぼれた油が染み込んだ布や紙などを、長い間風通しの悪い場所に積んでおい たとき。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(5) |
容器の油に不乾性油を混合したとき。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
解説 |
(4)が正しい | |||||||||||||||||||||||||||
| 容器からこぼれた油(乾性油)が染み込んだ布や紙などを、長い間風通しの悪い場所に積んでおい たとき、酸化熱で自然発火が起こることがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 問題35 | 製造所又は一般取扱所において、一般に行われる防火対策とそれにかかわりのある用語と して、次のうち関連のないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(1) |
反応槽内を窒素で置換する。 | ・・・・・・・ | 燃焼範囲 | |||||||||||||||||||||||||
|
(2) |
電動機を防爆構造とする。 | ・・・・・・・ | 引火 | |||||||||||||||||||||||||
|
(3) |
反応がまの温度を制御する。 | ・・・・・・・ | 反応速度 | |||||||||||||||||||||||||
|
(4) |
反応させる物質の注入速度を調整する。 | ・・・・・・・ | 燃焼範囲 | |||||||||||||||||||||||||
|
(5) |
作業時床面に散水する。 | ・・・・・・・ | 静電気 | |||||||||||||||||||||||||
|
解説 |
(4)が誤り | |||||||||||||||||||||||||||
| 反応させる物質の注入速度を調整するのは静電気対策のためである。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 例題集 NO10 問題 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright © 2015 ky-kikaku All rights reserved. | ||||||||||||||||||||||||||||